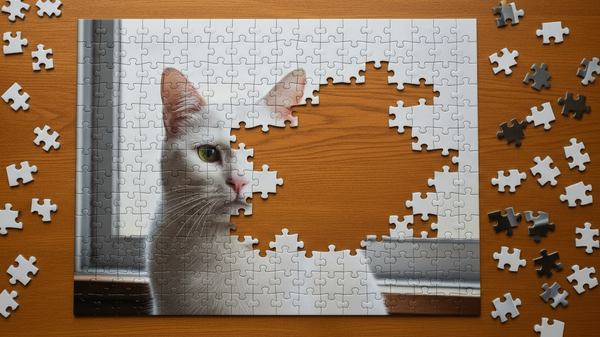「ポリアンナ効果」が記憶を歪める
人の脳はネガティブな情報よりもポジティブな情報を優先的に処理する。この認知バイアスが記憶の形成を歪め、時に問題解決を妨げる。心理学が明らかにした「よかった探し」の光と影。

小説『ポリアンナ』が社会にもたらしたもの
1913年、アメリカの作家エレナ・ポーター(Eleanor H. Porter)が発表した小説『ポリアンナ(Pollyanna)』は、両親を亡くした孤児の少女が「よかった探しゲーム(Glad Game)」を実践する物語である。このゲームは、牧師だった父が娘に教えたものだった。主人公ポリアンナは、どんな状況に直面しても、そこから少なくとも1つのよかったことを見つけ出そうとする。そしてこのゲームは彼女だけのものではなく、気難しい叔母、病を患う隣人、町の偏屈者といった周囲の人々を次々と変えていく。彼女の無邪気な楽観主義が、閉ざされた心を開き、町全体を明るく変えていく——この人間関係の変容こそが、物語を単なる教訓話以上のものにした。
この小説は世界的なベストセラーとなり、出版から数年で100万部以上を売り上げた。続編が書かれ、映画化も繰り返され、「ポリアンナ」という名前は英語圏で「過度に楽観的な人」を指す一般名詞として定着した。日本では1953年に村岡花子訳『少女パレアナ』として出版された。その後、1960年のディズニー実写映画を機に「ポリアンナ」という表記が広まり、1986年のアニメ『愛少女ポリアンナ物語』でさらに定着した。20世紀前半のアメリカにおいて、この物語は児童文学でありながら子どもだけでなく大人をも魅了し、単なる読み物の枠を超えて、ポジティブな思考様式そのものを象徴する文化的アイコンとなった。
そして小説の発表から約65年後の1978年、心理学者たちはこの「よかった探し」が単なる物語上の美徳ではなく、人間の脳に組み込まれた認知的傾向であることを実証することになる。
ポリアンナ効果:脳はポジティブに偏る
1978年、心理学者マーガレット・W・マトリン(Margaret W. Matlin)とデビッド・J・スタング(David J. Stang)は、人間の認知システムに普遍的なバイアスが存在することを示した。彼らはこれを「ポリアンナ効果(Pollyanna Principle)」と名付けた。この効果は、脳が好ましい情報を、不快な情報よりも正確かつ効率的に処理する傾向があることを指す。
その後の研究により、ポリアンナ効果は複数の認知プロセスにおいて確認された。人はポジティブな刺激に自分を晒し、ネガティブな刺激を避けようとする。不快または脅威的なものの認識には時間がかかる。ポジティブな刺激に遭遇した頻度を実際よりも高く報告する。そしてこの選択的な記憶の想起は時間が経つほど顕著になり、過去の経験を実際よりもバラ色に記憶する。
実はこの効果の萌芽は、マトリンとスタングよりも前、1969年にジェリー・D・ブーシェ(Jerry D. Boucher)とチャールズ・E・オズグッド(Charles E. Osgood)が「ポリアンナ仮説」として提唱していた。しかし1978年の研究によって、この仮説は包括的な認知理論として体系化された。
2015年、バーモント大学のピーター・シェリダン・ドッズ(Peter Sheridan Dodds)らの研究チームは、このバイアスが文化を超えて普遍的であることを示した。彼らは10の言語、10万語以上を分析し、すべての言語においてポジティブな語彙がネガティブな語彙よりも頻繁に使用され、より多様であることを発見した。ポリアンナ効果は、特定の文化圏に限定された現象ではなく、人類に共通する認知特性と思われる。
注意の偏りが記憶の偏りを生む
ポリアンナ効果が記憶に与える影響は、情報処理の段階から始まる。認知心理学者のタニヤ・B・トラン(Tanya B. Tran)とポーラ・T・ハーテル(Paula T. Hertel)の研究は、解釈のバイアスが記憶のバイアスを生み出すことを示した。人は日々、膨大な情報に晒されているが、そのすべてを等しく処理することはできない。脳は注意を向けるべき情報を選別し、その選別にポジティブバイアスが作用する。
ネガティブな情報を認識するには、ポジティブな情報よりも長い処理時間を要する。そのため、ネガティブな情報が記憶として定着する機会は減少する。注意が向けられなかった情報は、記憶に残りにくい。つまり、いま注意を向けた情報が、将来の記憶の内容を決定する。
興味深いことに、このバイアスは年齢とともに増加する。高齢者は若年者よりも強いポジティブバイアスを示す。これは単なる認知機能の低下ではなく、スタンフォード大学のローラ・L・カーステンセン(Laura L. Carstensen)らの研究が示すように、高齢者が意図的にネガティブな情報から注意をそらし、ポジティブな情報に焦点を当てる傾向が強まることによる。加齢に伴う感情制御の変化が、記憶の内容を形成する。
この連鎖は、人が「何を覚えているか」だけでなく「何を覚えていないか」をも決定する。ポジティブバイアスは記憶の欠損を生み、その欠損は本人には認識されない。
問題解決を妨げる認知の罠
ポリアンナ効果は精神的健康に寄与する側面がある。ポジティブな情報に焦点を当てることは、ストレスの軽減やレジリエンスの向上につながる。しかし同時に、この認知バイアスは問題解決を阻害する可能性を持つ。
直面した問題の中に微細な良い部分を見つけ、それで自己満足してしまえば、問題の本質的な解決には至らない。現状より悪い状況を想定して「まだマシだ」と自己正当化し、改善の必要性を感じなくなる。失敗から学ぶべき教訓は、ネガティブな情報として注意が向けられにくく、記憶に定着しない。結果として、同じ過ちを繰り返すリスクが高まる。
こうした、ポジティブバイアスが過度に働いて問題解決を妨げる状態は、「ポリアンナ症候群(Pollyanna Syndrome)」と呼ばれることがある。ただし、この用語は一般的な言説やビジネス文脈で使用されるものであり、精神医学や臨床心理学における正式な診断名ではない。DSM(精神疾患の診断・統計マニュアル)やICD(国際疾病分類)には収録されていない。むしろこれは、ポリアンナ効果が過度に作用し、現実認識を歪めている状態を指す比喩的表現と理解すべきである。
学術的に確立しているのは「ポリアンナ効果」という認知バイアスそのものであり、それが極端になった場合の問題を「症候群」と呼ぶことは、あくまで俗称に過ぎない。しかし便宜的であれ、この呼称が指し示す現象——過度の楽観が問題解決を妨げる状況——そのものは無視できない。
ポジティブであることの危うさ
ポリアンナ効果は、人間の認知システムに深く組み込まれた特性である。それは完全に排除できるものではなく、排除すべきものでもない。実際、うつ病や不安障害の患者はポリアンナ効果の例外であり、ネガティブバイアスを示す。適度なポジティブバイアスは、精神的健康の指標の一つと言える。
しかし現代社会は、この認知バイアスをさらに加速させる。「前向きに考えよう」「ポジティブ思考が大切」といった言葉は、自己啓発書からSNSの投稿まで、至るところに溢れている。前向きであることが美徳とされ、ネガティブな感情や思考は忌避すべきものとみなされる。こうした風潮は、ポリアンナ効果が本来持つ認知の歪みをさらに強化し、問題の本質から目を背けることを正当化しかねない。
「よかったこと」を見つける能力は、人生を豊かにする。だが問題の中のよかった部分だけを見て満足すれば、問題そのものは放置されたままになる。記憶が自動的にポジティブな情報を選び取るならば、意識的にネガティブな情報にも目を向ける努力が求められる。失敗から学ぶには、失敗をありのままに記憶する必要がある。
ポリアンナが教えてくれたのは、逆境の中にも希望を見出す強さである。しかし心理学が明らかにしたのは、その強さが時に現実認識を歪めるという事実である。「ポジティブであること」が無批判に称揚される社会において、私たちは問うべきである。記憶が「よかったこと」を選び取るとき、私たちは何を見落としているのか、と。
English version is available on Medium: The “Pollyanna Effect” Distorts Memory | Ki to Oku Annex