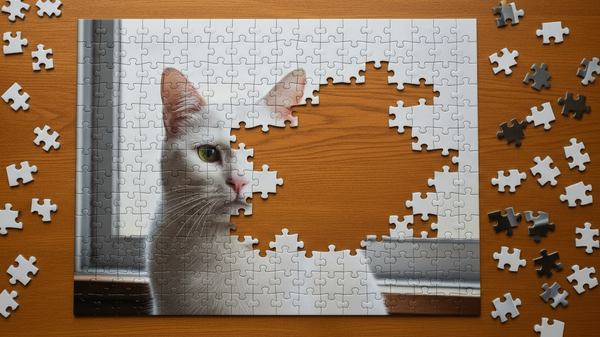ギリシャ神話はなぜ記憶の女神ムネーモシュネーと忘却の化身レーテーを生んだのか
ギリシャ神話には記憶の女神ムネーモシュネーと忘却の化身レーテーが登場する。記憶は文明を支える力として、忘却は得体の知れない力として、神話の中に位置づけられた。

神話に登場する神々
ギリシャ神話と聞くと、ゼウスやアテナが登場する壮大な物語を思い浮かべるだろう。現代の私たちにとって、それは映画や小説のように楽しむ架空の物語だ。しかし古代ギリシャ人にとって、神話は物語ではなく宗教そのものだった。各地に神々を祀る神殿が建てられ、人々は祭祀を通じて神々に祈りを捧げた。
聖書のような統一的な聖典はなく、教義もなく、各地で独自の祭祀が行われていた。神話には地域や時代によって多様なバージョンが存在したが、ここでは主に、古代ギリシャの詩人ヘシオドスが神々の誕生と系譜を歌った叙事詩『神統記』と、哲学者プラトンが理想国家を論じた対話篇『国家』に記された物語を扱う。
そこには、記憶と忘却が神々の系譜の一部として語られている。ヘシオドスの『神統記』によれば、ムネーモシュネー(Mnemosyne)という記憶の女神は、天空神ウーラノスと大地の女神ガイアの娘であり、ティターン神族の一人とされる。一方、忘却を表すレーテー(Lethe)は、争いの女神エリスの娘とされた。
雷や嵐を司るゼウス、海を司るポセイドンのように、目に見える自然を司る神々がいた。愛の女神アフロディーテや平和の女神エイレネのように、抽象概念を神としたものもいた。だがムネーモシュネーとレーテーが象徴する記憶と忘却は、愛や平和のように肯定的な価値として扱われる概念ではなく、個人の内面で自然に生じる制御しがたい現象である。なぜ、このような概念が神々の系譜の中に位置づけられたのだろうか。
ムネーモシュネー:口承文化における記憶の女神
ムネーモシュネーは単に記憶を象徴する存在ではない。『神統記』によれば、彼女はゼウスと九夜を共にし、九人のムーサイ(Muses)を産んだとされる。ムーサイは詩、音楽、舞踊、天文学、歴史など、あらゆる学芸を司る女神たちである。つまり、ギリシャ神話において記憶は文化と知識の源泉そのものとして位置づけられていた。
古代ギリシャは文字を持ちながらも、依然として口承文化の影響が強く残る社会だった。詩人は長大な叙事詩を暗唱し、哲学者は対話を通じて思索を深め、歴史家は出来事を記憶によって保持した。古代ギリシャ最古の叙事詩『イリアス』や『オデュッセイア』も、元々は口承詩として暗唱され、後に文字で記録された作品である。
ムネーモシュネーがティターン神族という古い世代の神として位置づけられた背景には、古代ギリシャ人の神格化に対する独特の考え方があった。紀元前1世紀の歴史家ディオドロス・シクルスは『歴史叢書』の中で、ティターン神族について次のように記している。「彼らの各々は、人類に利益をもたらすものの発見者であり、すべての人々に与えた恩恵ゆえに、栄誉と永遠の名声を授けられた」。ディオドロスはエウヘメリズム(神々はかつて偉大な人間であり、死後に神格化されたとする説)の立場を取る歴史家であり、神話を人間の歴史として合理的に解釈しようとした。
ムネーモシュネーの場合、その恩恵とは記憶そのものだった。ディオドロスによれば、彼女は「理性の力の用法を発見し、私たちの周囲のあらゆる対象に名前を与え、それによって私たちが意思を表現し、互いに会話することを可能にした」という。つまり、言語と思考の基盤となる記憶の能力を人類にもたらしたとされたのである。
口承文化において、記憶は文明の存続を左右する力だった。吟遊詩人(詩を語り継ぐ職業的な語り手)たちは叙事詩を語る前に、必ずムネーモシュネーに呼びかけた。これは単なる形式ではなく、記憶が個人の努力だけでは獲得できない、神から与えられる力だと信じられていたからである。
プラトン(紀元前4世紀の哲学者)も、自身の著作の中で過去の出来事を語る際、「詩人たちのように、ムーサイとムネーモシュネーに助けを求めなければならない」と記している。正確に思い出すために女神の力を借りる、という伝統が、文字文化が優勢になった後も残っていたのである。
レーテー:忘却の化身
レーテーは、ムネーモシュネーとは異なり、神ではない。ヘシオドスの『神統記』では争いの女神エリスの娘として系譜に登場し、プラトンの『国家』では冥界に流れる川として描かれる。つまり、神話の中で忘却を表す存在ではあるが、神としての地位は与えられていなかった。
『神統記』において、エリスの子どもたちには、苦痛(ポノス)、破滅(アテ)、飢餓(リモス)、殺人や嘘を表す存在など、忌まわしいものが並ぶ。忘却を表すレーテーもまた、そうした否定的な存在の一つとして位置づけられていた。
一方、プラトンの『国家』第10巻では、レーテーは冥界に流れる川として描かれている。死者の魂は次の生を選び、この川の水を飲んで前世の記憶を洗い流してから再び生まれ変わる。ここでレーテーは、転生のために必要な装置として機能している。前世の記憶を保持したまま生まれ変わることはできない。魂は一度すべてを忘れ、白紙の状態で新しい人生を始めなければならない。
オルペウス教などの神秘宗教では、レーテーは泉として描かれ、避けるべき罠とされた。オルペウス教の教えによれば、死者は冥界でレーテーの泉とムネーモシュネー(記憶)の泉、二つの水源のどちらから水を飲むかを選択できるとされた。レーテーから飲めば前世を忘れ、再び地上に生まれ変わる。しかしムネーモシュネーから飲めば前世を記憶し、輪廻転生の苦しみから解放されるという。
この記憶と忘却の対比は、神話だけでなく実際の宗教儀礼でも実践されていた。古代の旅行家パウサニアスは、レバデイアにあるトロフォニオスの神託所について記録している。神託を受ける者は、まずレーテーの水を飲んで日常の記憶を洗い流し、次にムネーモシュネーの水を飲んで神託の内容を記憶した。記憶と忘却は、神話の中だけでなく、儀礼を通じて人々の生活に根付いていたのである。
なぜ抽象概念は神話に組み込まれたのか
ムネーモシュネーとレーテーは、どちらも抽象概念が神や精霊とされた例である。しかし、両者がそのように扱われた理由は異なっていた。
ディオドロス・シクルスが記録したように、ティターン神族は「人類に利益をもたらすものの発見者であり、すべての人々に与えた恩恵ゆえに、栄誉と永遠の名声を授けられた」。ムネーモシュネーは、理性の使用と言語という能力を人類にもたらしたとされ、その恩恵ゆえに神として崇められた。
一方、レーテーは苦痛、破滅、飢餓といった否定的な概念とともにエリスの子として記されている。人類への恩恵ではなく、むしろ避けたい存在である。古代ギリシャには、こうした否定的な概念を含め、抽象概念を神々の系譜の中に組み込んだ例が数多くあった。正義や平和だけでなく、眠り、死、老いといった、人間が制御できない現象も、それぞれが神や神の子孫として語られた。
こうした抽象概念を表す存在は、古代ギリシャでは「ダイモーン」と呼ばれた。ダイモーンとは、神々と人間の中間に位置する霊的存在の総称である。古代ギリシャ人は、日常生活の中で自分たちに影響を与える何らかの力を感じていた。しかし、その力が何であるのか、どの神によるものなのか特定できないとき、彼らはそれを「ダイモーン」と呼んだ。忘却もまた、そうした得体の知れない力の一つだった。人は覚えておきたいことを忘れ、忘れたいことが記憶に残り続ける。古代ギリシャ人は、このような予測不可能で制御不可能な現象をダイモーンとして神話に組み込むことで、名前を与え、理解しようとしたのである。レーテーはまさにこのダイモーンの一つだった。
つまり、古代ギリシャ人にとって、抽象概念を神話に組み込むことには二つの異なる意味があった。一つは恩恵への感謝であり、もう一つは理解の手段だった。ムネーモシュネーとレーテーの神話は、人間が自らの内面で起こる現象を、神や霊的存在という形を借りてどのように理解しようとしたのか、その試みの記録である。
English version is available on Medium: Why Greek Mythology Created Mnemosyne and Lethe | Ki to Oku Annex